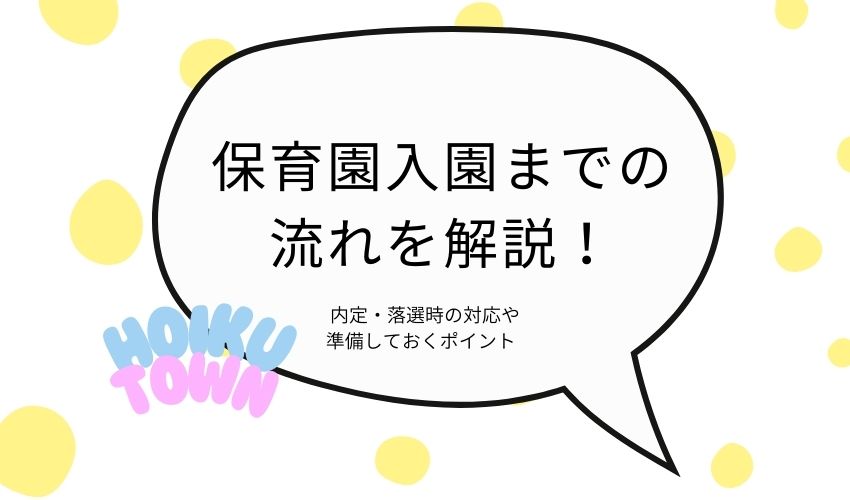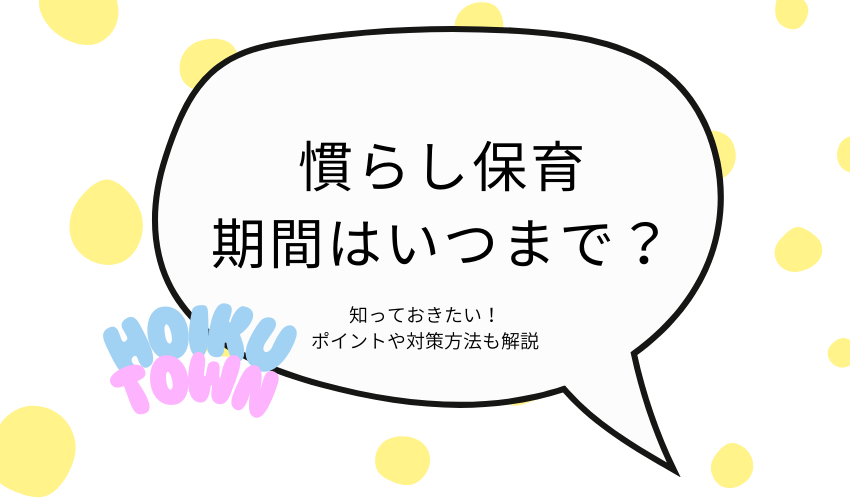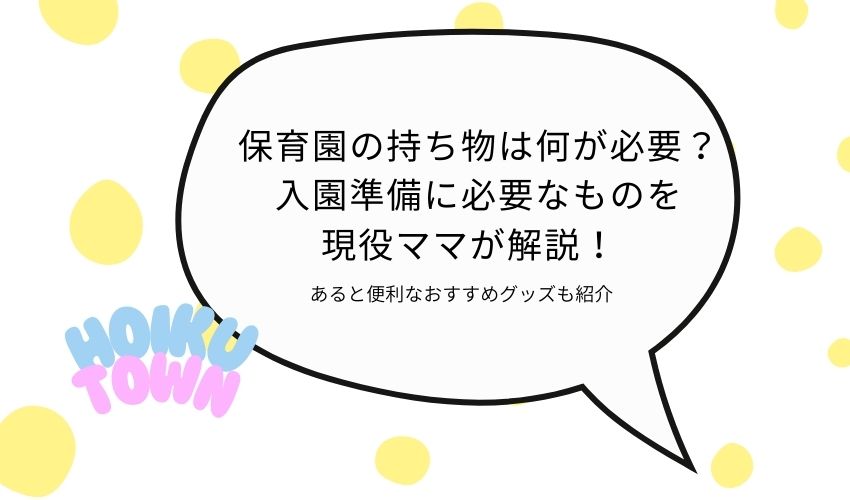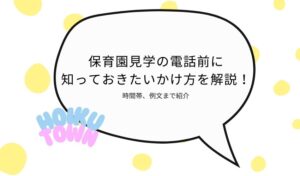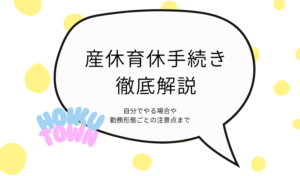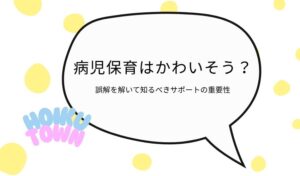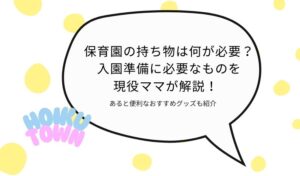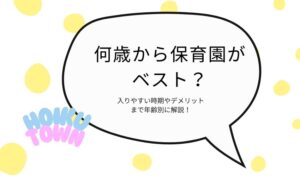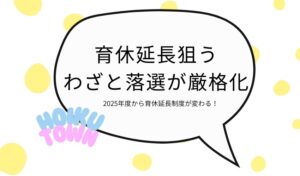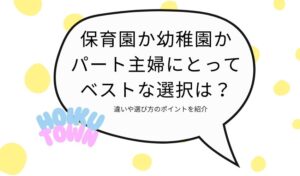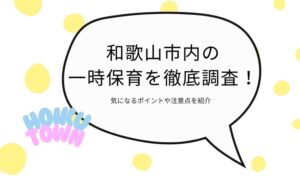保育園、いつから動き出せばいいんだろう?
申込みの準備は万全かな?
もし落選したらどうしたらいいの?
育休中のママ・パパにとって、保育園に入園できるかどうかは非常に重要な問題です。
職場復帰や保育園への入園に不安や疑問も多く、何から始めればよいのか戸惑う方も多いでしょう。
保育園入園までの流れが分かれば、持ち物を準備する際にも素早く対応できます。
そこで本記事では、保育園に入園するまでの流れを詳しく紹介します。
さらに内定後の準備から万が一の落選時の対応まで、実践的なポイントを解説するため要チェックです。
保育園入園までの流れは?
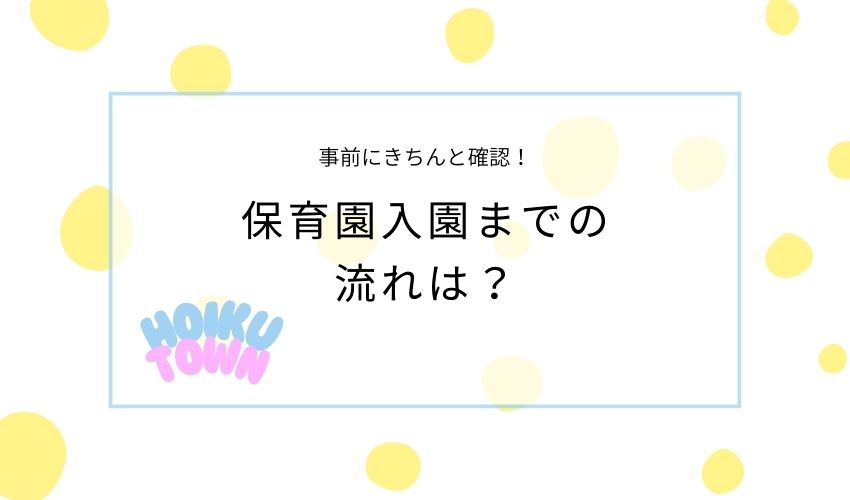
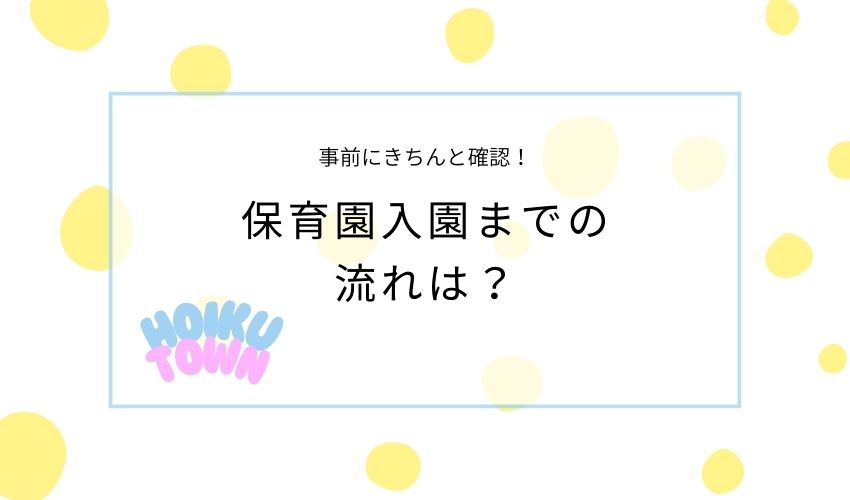
保育園入園までの流れは、大きく4つのステップに分かれます。
- スケジュールを立てる
- 情報収集
- 申込み
- 通知結果が届く
それぞれ以下で詳しく解説します。
①スケジュールを立てる
保育園入園に向けたスケジュールは、職場復帰の時期を起点に考えます。
育休中の方は復帰予定日から、逆算して準備を進めましょう。
申し込みの時期は、各自治体・入園希望時期によって対応が異なるため注意が必要です。
- 4月入園希望の場合
- 前年10月頃から申し込みを開始する自治体が多い
- その他(4月以外)入園希望の場合
- 各自治体によって異なるが、入園希望の2.3ヶ月前から申し込みが可能なケースが多い
入園後についても、各自治体で利用可能な開始時期が決まっています。
慣らし保育などもあるため、お住まいの自治体の条件を確認しながら、なるべく余裕を持ったスケジュールを立てましょう。
②情報収集
保育園選びのポイントは、情報収集が非常に重要なポイントを担います。
- 市役所や区役所の保育課
- 地域ごとの保育園情報や申込み要項について説明を受ける
- 自治体施設のホームページ
- 各園の定員や特徴、過去の入園実績なども確認する
- すでに保育園に子どもを通わせている知り合いから実際の声を聞く
- 園の雰囲気や先生の対応、行事ごとの回数など
入園後「思っていたのと違う…」と後悔を防ぐためにも、情報はできる限り集めておきましょう。
上記の方法を組み合わせて行うのがおすすめです。
③申込み
4月入園の場合、多くの自治体では10月頃から受け付けが開始します。
申込みの際は必要書類を漏れなく準備しましょう。
必要書類は各自治体や申請理由によって異なります。
以下では、和歌山市の就労を目的とした際の必要書類を記載していますので、参考にしてください。
- 就労証明書・申告書
- 施設型給付費等教育・保育給付認定申請書
- 発達状況表
- 母子手帳
- 個人番号確認書類及び本人確認書類
その他、家庭の状況により書類や証明書が必要です。
書類に不備があると受付ができないため、自治体の窓口で事前確認をしておきましょう。
④通知結果が届く
4月入園の場合、多くの自治体では2月頃に入園選考の結果通知が届きます。
通知を受け取ったら内容を確認し、入園が決まった場合は速やかに必要な手続きを進めましょう。
入園説明会や面接の日程が指定されている場合もあるので、見落とさないように注意が必要です。
保育園入園が決まった場合の流れは?
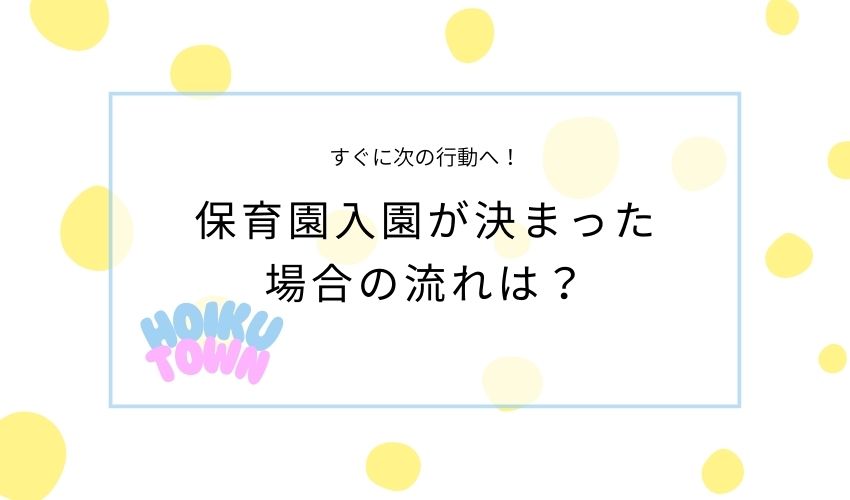
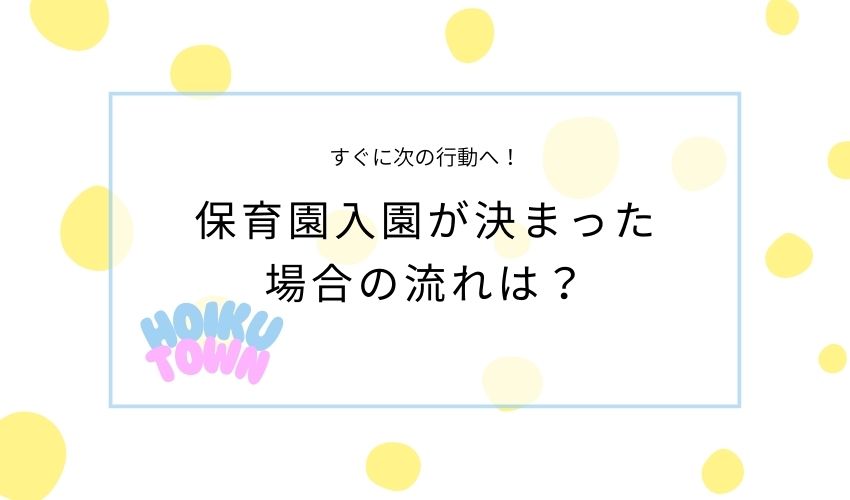
保育園入園が決まったら、迅速に以下の行動を進めましょう。
- 職場へ保育園の入園が決定した報告
- 入園前の説明会や健康診断への参加
- 保育園から指定された持ち物の準備
それぞれ以下で詳しく解説します。
各施設や年齢によって準備物が異なるため、持ち物の準備も入園説明会の後が無駄がなく用意しやすいでしょう。
職場に報告をする(復帰時期の調整)
職場への報告は可能な限り早めに行いたいですが、復帰時期と勤務時間の調整は慎重に行いましょう。
多くの保育園では入園直後に1〜2週間程度の慣らし保育期間を設けます。
そのためフルタイムでの即時復帰は難しく、可能であれば入園説明会後に流れを把握し復帰の日程調整ができるとベストです。
慣らし保育について詳しく知りたい方はこちらも参考にしてください。
また、自治体によっては入園月からの職場復帰に条件があるため、事前に確認しておきましょう。
人事や総務部門と綿密なコミュニケーションがスムーズな職場復帰のポイントです。
入園前の説明会や健康診断に参加する
入園が決まると、説明会や面談、健康診断などの案内が送られます。
これらは入園に向けた重要な準備の一つとなるため、必ず参加しましょう。
入園説明会では園で生活を送るうえでのルールや、必要な準備物の詳細について説明を受けます。
園によっては説明会が子連れ不可になっている場合があるため、事前に確認しておきましょう。
必要な道具を揃える
保育園から渡される持ち物リストに基づいて、必要なものを揃えていきます。
施設や子どもの年齢によって必要な物が異なるため、リストは慎重にチェックします。
そしてすべての持ち物には必ず記名が必要です。
特に衣類や布団などは他の子どもも同じようなものを持っている場合があるため、分かりやすい場所にはっきりと記名してください。
手作りの用品がある場合は、早めに取り掛かりましょう。
万が一保育園に落選した場合の流れは?
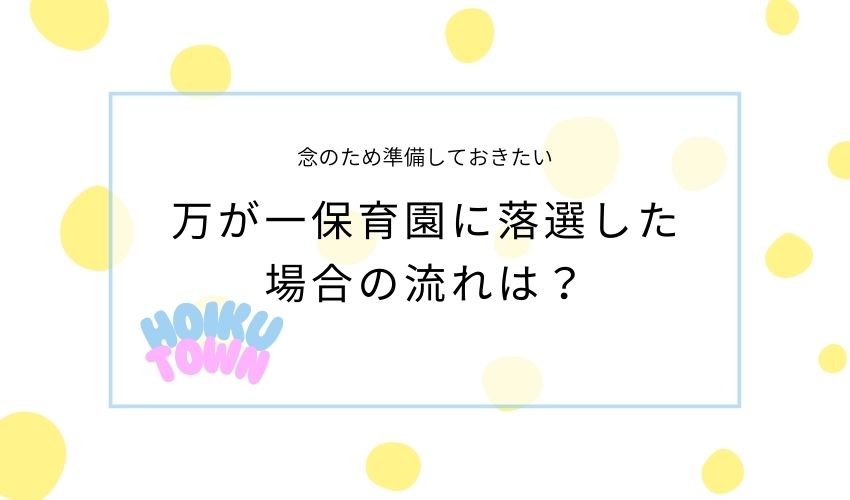
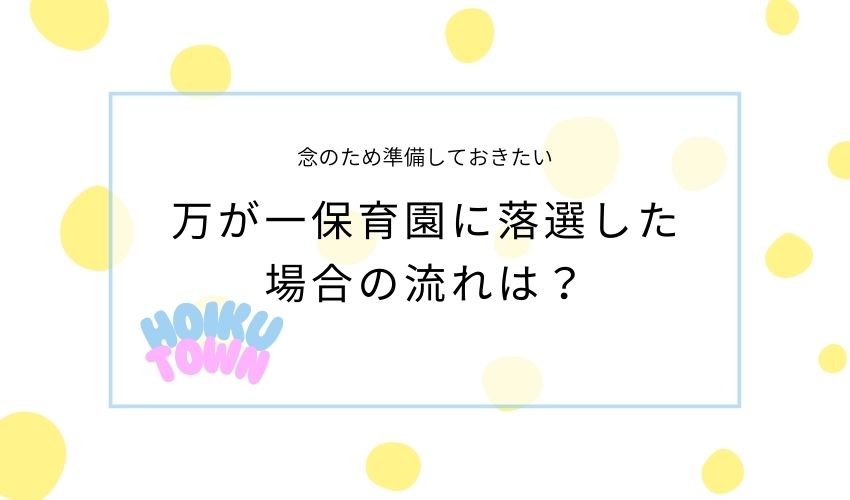
万が一保育園に落選した場合でも、いくつかの選択肢があります。
- 二次募集へ申し込む
- 認可外の保育園も検討する
- ベビーシッターや一時保育を利用する
- 会社と育休延長制度について相談する
状況に応じて、複数の対応策を組み合わせながらベストな対応策を選択しましょう。
二次募集へ申し込む
多くの自治体では一次募集で定員に空きが出た園で二次募集を行います。
申込み期間は自治体によって異なりますが、2月下旬から3月上旬に行われるケースが一般的です。
一次募集で落選した場合は、すぐに市区町村の窓口で二次募集の情報を確認しましょう。
認可外の保育園も検討する
認可外保育園は、認可保育園に比べて入園のハードルが低い傾向です。
認可外といっても都市部を中心に企業主導型保育園や小規模保育園など、さまざまな形態の施設があります。
自治体の指導を受けている施設も多く、保育の質は一定水準に保たれており安心です。
ただし、保育料が認可保育園より高くなるケースも想定されるため、費用面も含めて検討しましょう。
ベビーシッターや一時保育を利用する
一時的な対応として、ベビーシッターサービスや一時保育の利用を検討するのもよい選択肢です。
特にベビーシッターは、利用時間や場所の融通が利きやすく、急な対応も可能です。
自治体によっては利用料の補助制度があるため、あわせて確認しましょう。
会社と育休期間の延長を相談する
保育園が決まらない場合は、育児・介護休業法に基づき、最長2歳まで育休を延長できる場合があります。
会社の人事部門に相談し、育休延長の手続きや条件について確認しましょう。
ただし、延長が認められた場合でも、並行して保育園探しを続ける必要があります。
意外とすぐに空きが出て、年度途中で入園できる場合もあるかもしれません。
筆者は一次で落選し、二次募集がなく困っていたのですが、1ヶ月後に希望の園に入園できた経験があります。
困った時はまず、お住まいの役場に相談しておくとよいでしょう。
保育園入園までに確認しておくポイント
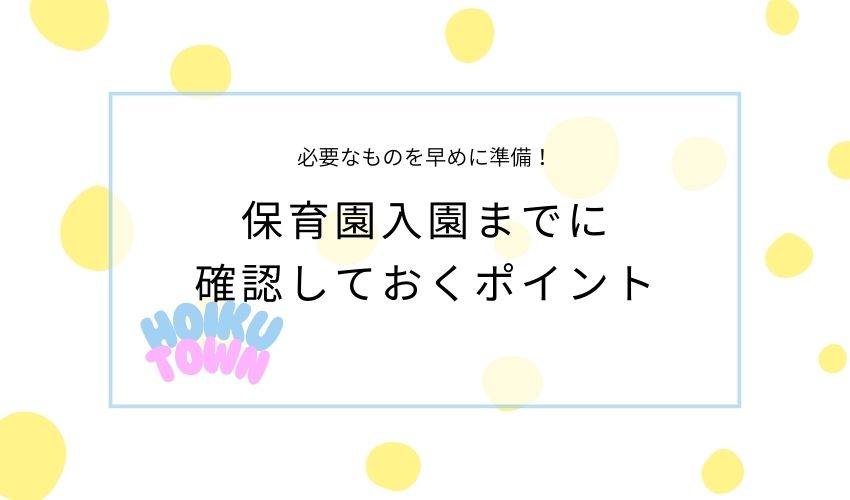
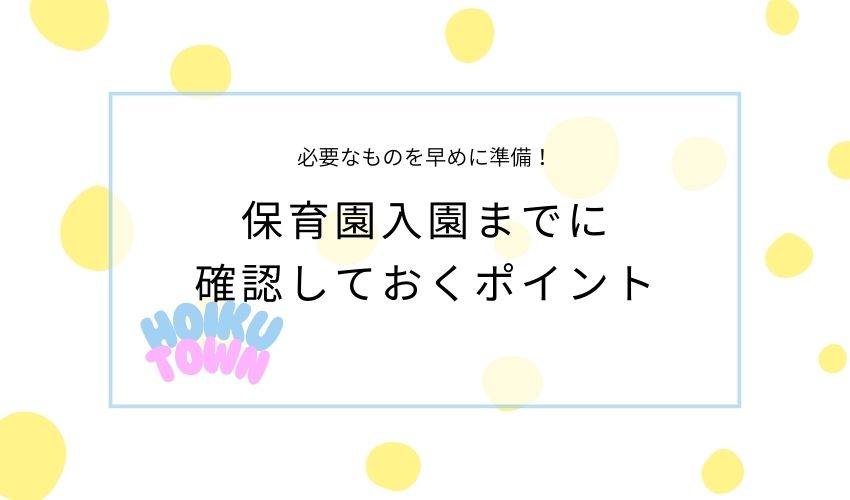
保育園入園に向けて、職場復帰後の生活を想定したスケジュールをイメージしておきましょう。
朝の準備から夕方のお迎え、夕飯・お風呂、子どもを寝かすまでの一通りはもちろんですが、通勤・帰宅時間がポイントです。
自家用車・公共交通機関、どちらも復帰前に一度同じ時間帯で練習しておくと安心です。
また、入園直後の慣らし保育は子どもの様子によって期間が長引く場合があります。
可能な限り、復帰の日程・勤務時間の調整が付きやすいスケジュールが組めるとよいでしょう。
さらに急な残業や電車の遅延なども考えられるため、延長保育の利用可否や時間帯の確認は必須です。
子どもの体調不良や保育園が休みの際に備え、複数の支援体制を整えておくと万が一の際も安心です。
- 家族、祖父母や友人などの頼り先
- 病児保育
- ファミリーサポート
- ベビーシッター
- 家事代行サービス
まとめ|順調な保育園入園準備がスムーズな職場復帰のコツ
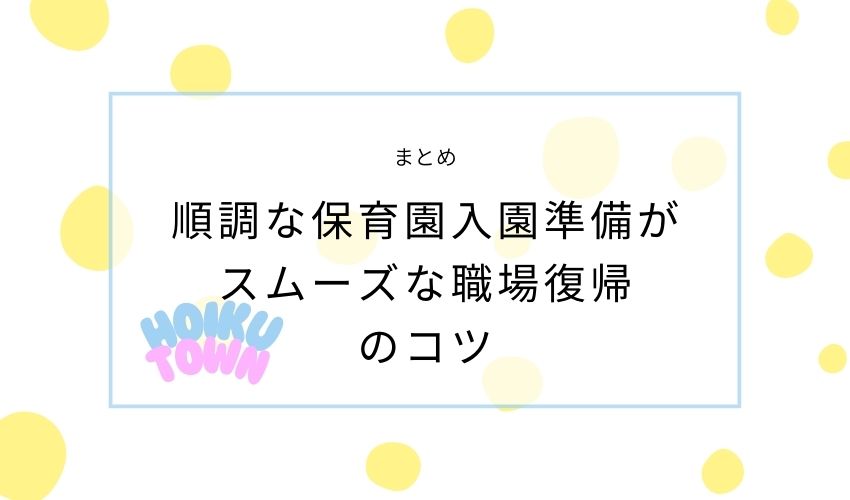
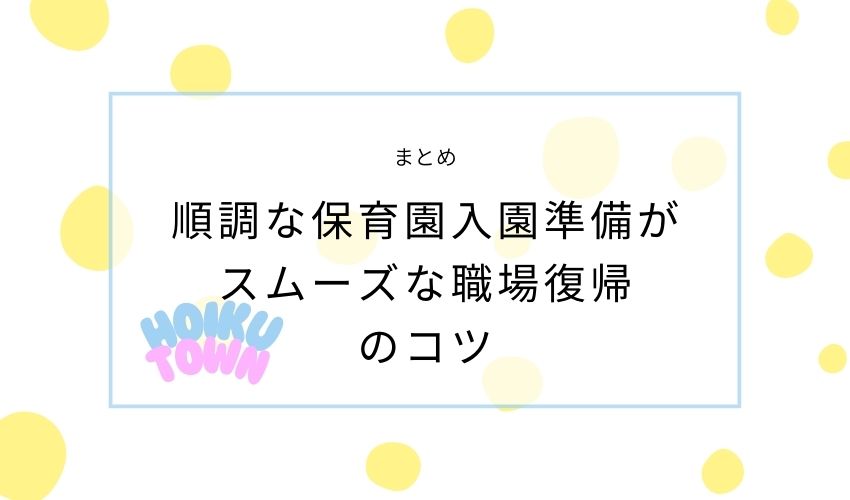
保育園入園をスムーズに行うためには、早めの情報収集と計画的な行動が鍵です。
入園が決まったあとは慣らし保育期間も考慮しつつ、職場との調整や必要な準備を進めましょう。
また、落選時の対処策や緊急時のサポート体制など、第二プランを用意しておけば安心して職場復帰が可能です。
本記事があなたのスムーズな職場復帰の参考になれば幸いです。